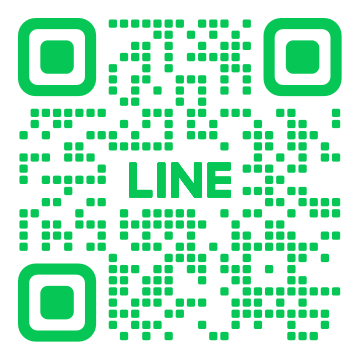これまで、相続登記は義務ではなく、任意で行うものでした。そのため、相続登記がされないまま放置されるケースが多く、不動産の所有者不明や所有権の争いなどが発生する問題がありました。
相続登記がされないまま放置されると、土地の所有者が分からなくなり、土地の利用や売却などが困難になる「所有者不明土地」が増加してしまいます。
また相続登記がされない場合、相続人同士で所有権の争いが発生する可能性があります。
相続登記が放置され、結果、所有者不明土地が増加すると、道路や鉄道などの社会インフラ整備が困難になる場合があります。
これらの社会的問題を解決するため相続登記が義務化されることになりました。
しかし、今まで任意だった相続登記がいきなり義務化されると、混乱が生じることから一定の経過措置がとられます。そこで以下経過措置や罰則の流れを簡単にまとめました。
経過措置
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
罰則
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の対象となります。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の適用対象となります。
罰則の流れ
登記官が、義務違反を把握した場合、まず義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します)
催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
上記の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
過料の金額
通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。
相続登記を行わないことの正当理由とは
(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合